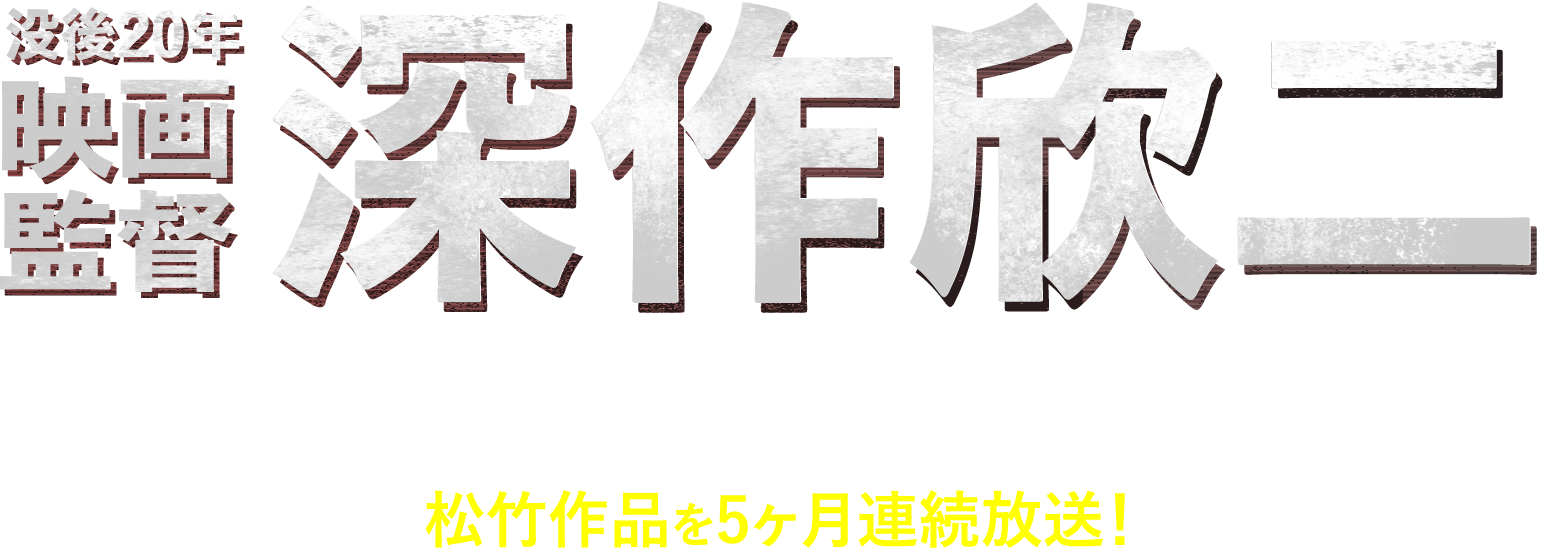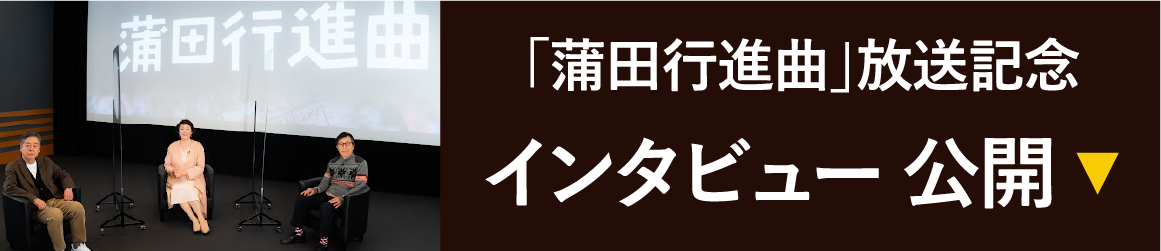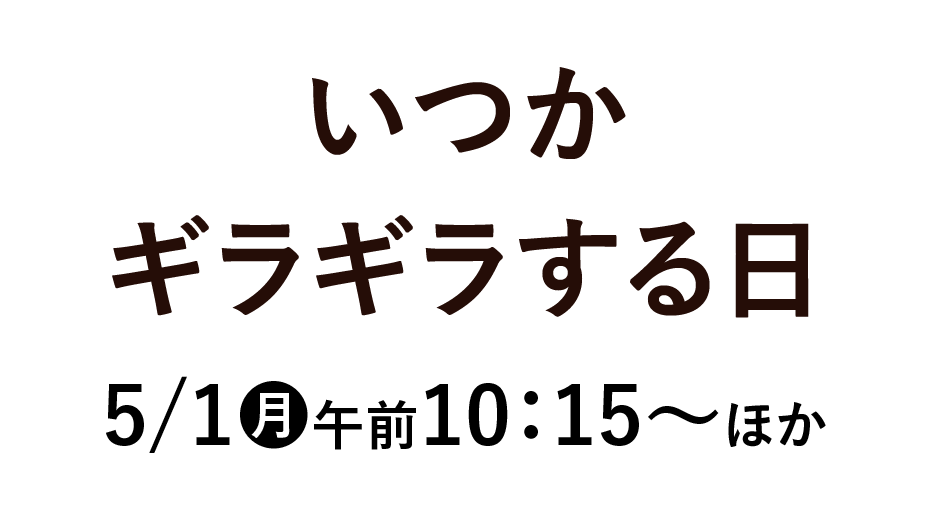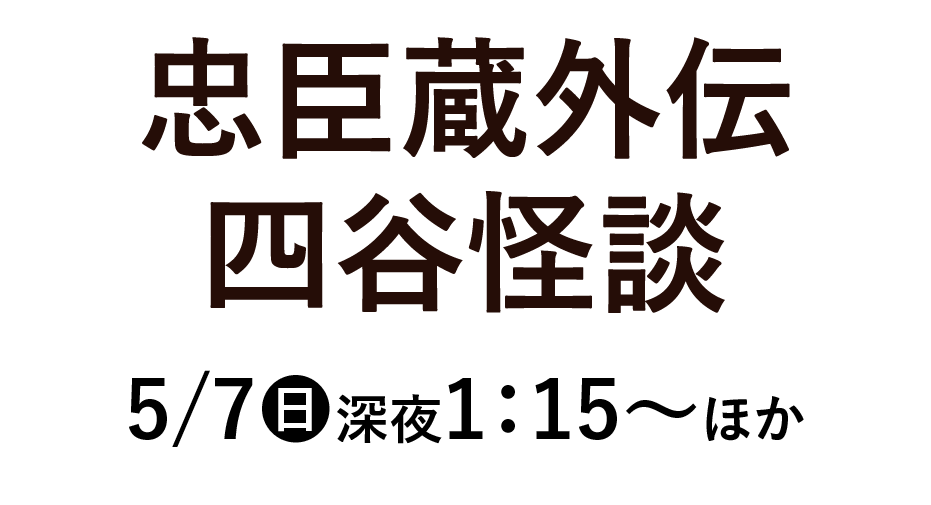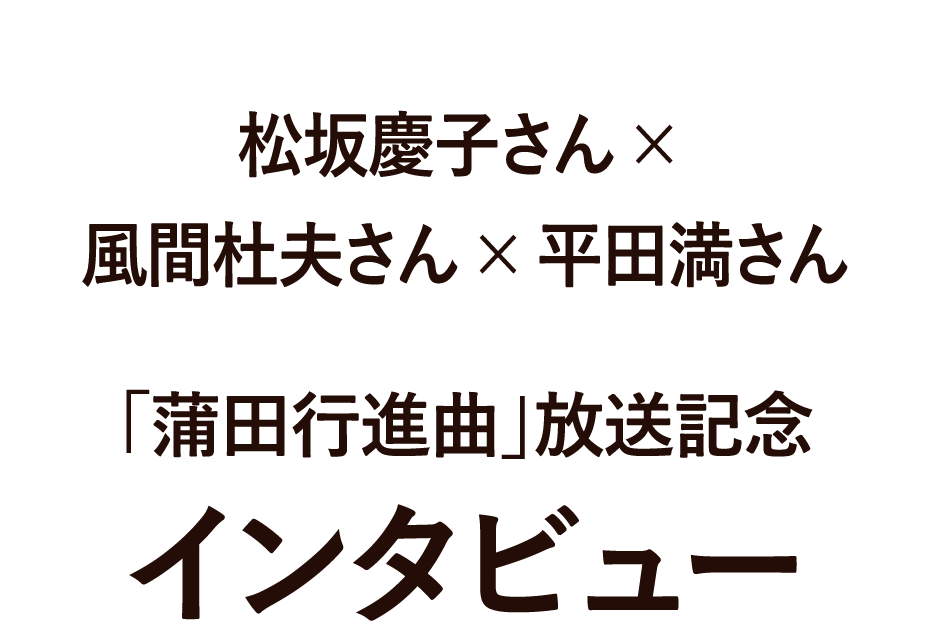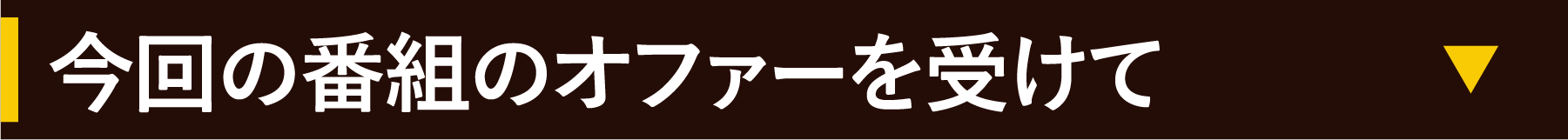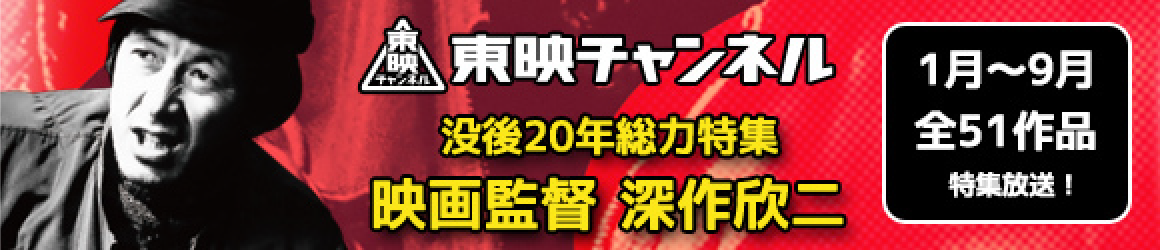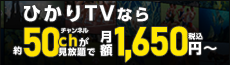松坂:小夏はひとつの役柄と捉えていたのですが、いま『蒲田行進曲』を見ると、小夏の人生に私の人生のほとんどが入っているなって思うんです。女優として生きていた私と、結婚して「毎日が日曜日!」といった感じで、日々の小さな幸せをかみしめて生きていた私と、その両方が小夏にはあって、私の将来を予知するような役だったんだなって、いまになって運命を感じますね。
風間:ヤスが銀ちゃんに対して「銀ちゃんカッコいい!」って言いながらも、「あいつのせいで何でおれがこんな目にあわなければいけないんだ!」という愛憎の思いを抱くのだけど、あの感情は僕個人がつかこうへいという人に対して抱いていたものと同じなんです。「つかさんカッコいい!」という思いもあるのだけど、「なんであいつにこんな思いをさせられなくちゃいけないんだ」という気持ちになったことも多々ありました。僕にとってのつかさんが銀ちゃんで、僕はヤスだったなあと思います。
平田:『蒲田行進曲』は僕にとって空前絶後の作品です。『蒲田行進曲』があるからいまの僕があるわけで、それ以前にもあんな経験をした映画はなかったし、その後もそうそうなかったなと思います。いろいろなものが詰まっているんですよね。いろいろな人の思いも、いろいろなあの手この手も詰まっている映画だなと思います。
松坂:撮影が始まって2週間くらい経って、それまで収録した分をラッシュという形で試写を見たときに、きらきらと光る風が吹いたような印象を受けて、新しい映画になりそうだと感じた覚えがあります。
風間:ラッシュのとき、たしか角川春樹さんだったと思うのだけど「役者の熱気が初めてフィルムに焼き付けられた」とおっしゃっていて、その言葉が記憶に残っています。画期的な作品だったのでしょうね。
松坂:そういえば深作監督が、「映画の熱気は、現場が10あったとしても、10は映し出されない」とお話されたことがあって、そのときに私も、熱気が10あっても映るのは7くらいになっちゃうのかもしれないなって思ったんです。角川さんのそのお言葉からすると、『蒲田行進曲』は熱気が10、全部出たのかもしれないわね。初めて熱気が10焼き付けられた映画ができて、深作監督もうれしかったでしょうね。
平田:やっているほうはいっぱいいっぱいだったけど、やってて楽しかったですね。おっしゃるように撮影所自体、熱気がありました。クランクアップしたときはほっとしましたし、出し尽くしたなという感覚がありました。正しくは、深作監督に出し尽くしていただいたわけですが。
松坂:クランクアップしたときには、東京に帰るときに淋しく思うだろうなって感じた記憶があります。東映京都撮影所は『青春の門』(1981年)でもお世話になったのだけど、もともと私は松竹出身だから最初のうちは借りてきた猫みたいにおとなしくしていたんです。東映京都撮影所は結髪さんをはじめ、スタッフは皆さん迫力があって緊張感があって、そんな中で当時の東映撮影所の所長だった高岩淡さんにはいろいろとお世話になりました。高岩さんは人格者でいらっしゃって、笑顔にさせてくださる太陽のような方だったんです。撮影するうちに高岩さんをはじめ、スタッフの皆さんとも花見小路にあるお店に連れていってもらって、歌を歌ったりして……。カラオケに行ったの私だけだったっけ?
平田:そんな余裕はありませんでしたよ(笑)。
風間:僕は、撮影がオールアップしたときに、「今日は俺がおごるぞ!」って言って、つかこうへい事務所の共演仲間を餃子の王将に連れていきました。「好きなもの食っていいぞ!」って言ったものの高が知れていて、安上がりでせこい銀ちゃんを地で行ったんです(笑)。それから車で、京都から東京まで役者仲間と交代で運転して帰りました。
平田:風間さんは車で京都に来ていたんですよね。撮影中は宿舎のホテルから撮影所まで、毎日風間さんの車に乗せていただいて、その節はありがとうございました。
風間:劇中、銀ちゃんの部屋に飾ってあった等身大の土方歳三のパネルが登場するのだけど、あのパネルを大道具さんが記念に下さるというので、京都から東京までの帰り道は、車の屋根に積んで持って帰りました。いまも僕の部屋に飾っています。
松坂:昨年、NHKのドラマ『一橋桐子の犯罪日記』を撮影していたときに、女性の助監督さんから「ここにいるスタッフはみんな『蒲田行進曲』を観ています」って言われました。その言葉を聞いて、エンターテインメントの世界で生きていく若者もベテランも『蒲田行進曲』を観ていて、改めてバイブルのような作品なんだなって感じたんですよね。そして今回お二方とお話して、『蒲田行進曲』に出演していた私たちにとって、この作品は40年以上経っても、色褪せない思い出を持ち続けることができる唯一無二の映画だなと実感しています!